![[Print Panel]](../images/print-panel.gif)
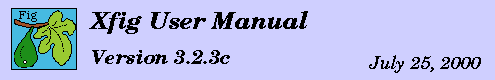
Fig ファイルの Export や Print のために、 xfig は Fig ファイルを望みの出力フォーマットに変換するための ポスト・プロセッサである fig2dev を呼び出します。 Export に際しては、PostScript、EPS、LaTeX、METAFONT や、 GIF、JPEG などのビットマップ・フォーマットを含む、 1ダース以上のフォーマットがサポートされています。 Export の章の Language の説明を参照して下さい。
これは、xfig とともに、fig2dev を インストールしておかなければならないことを意味します。 fig2dev は transfig パッケージの一部であり、 あなたが xfig を見付けた場所から入手できる筈です。 詳細については、xfig の入手とインストール を参照して下さい。
用紙の大きさとしては以下のものが使用可能です。
Single を選択した場合にはこの機能は使用されず、 用紙からはみ出した部分は単に失われます。
このデフォルト値は、リソース Fig*printer*string、 もしくは環境変数 $PRINTER で指定されたものとなります。
システムがプリンタを定義するために /etc/printcap を用いているならば、 この右側にメニューが置かれます。
デフォルトではこれは空ですが、必要であればリソース Fig*job-params*string を用いて設定することができます。
このボタンのラベルは、現在の図が印刷されるのか、 もしくはバッチ・ファイル内の図が印刷されるのかに応じて、 Print FIGURE to Printer、 もしくは Print BATCH to Printer のいずれかとなります。
プリンタへの出力に際して、xfig は、まず fig2dev プログラム を用いて図を PostScript に変換した上で、 その結果を lpr (System V システムにおいては lp) に 渡します。 lpr (もしくは lp) の実行に際しては、 PostScript Printer フィールドで指定されたプリンタ名と Print Job Params フィールドで指定されたオプションが コマンド行オプションとして渡されます。
バッチ・ファイルに格納された図は、 後で Print BATCH to Printer が実行されたときにプリンタに出力されます。 この機能は、 複数の図を一度にプリンタへ出力するために用いることができます。
xfig を LaTeX とともに使用するためのヒントについては LaTeX と Xfig を参照して下さい。
図を PostScript プリンタへ出力するためには Print を使用して下さい。
Language が GIF である場合には、 どの色を透明とするかを選択するメニューが現れます。
Language が JPEG (JFIF) である場合には、 ``quality factor'' を設定するためのフィールドが現れます。
以下のフォーマットが使用可能です。
ベクタ・フォーマット:
ビットマップ・フォーマット:
LaTeX フォーマットのバリエーションとして、 標準の picture 環境以外に、epic、eepic、 及び eepicemu マクロを使用することもできます。 Combined PostScript/LaTeX を用いると、図のテキストの部分を LaTeX で、 それ以外の部分を PostScript で出力することができますが、 これは特に図に複雑な数式が含まれている場合 (TEXT FLAGS も参照) に有用です。
xfig で作成することのできるすべての図を、 すべてのフォーマットにおいて完全に出力できるわけではありません。 例えば、取り込まれたイメージは IBMGL でのエクスポートに際しては出力されません。 PostScript でのエクスポートに際しては xfig のほとんどすべての機能が使用可能であり、 またかなり高品質の出力を生成することができます。
xfig と共に入手可能な TransFig パッケージの一部である fig2dev プログラムが、 Fig フォーマットからの実際の変換の処理を行ないます。
GIF や JPEG などのビットマップ形式でのエクスポートを行なうためには、 GhostScript、 及び netpbm パッケージ が必要となります。
デフォルトは None です。
このファイル名は、デフォルトでは図のファイル名に 出力のフォーマットに対応する拡張子を付け加えたものとなっていますが、 Output Filename でファイル名を指定して エクスポートを行なった場合にはそのファイル名に変更されます。
Output Filename フィールドのファイル名は、 Alternatives リストのファイル名をクリックするか、 もしくはキーボードから直接入力することによって変更することができます。 ファイル名を入力した後に return をタイプすると、 Export ボタンをクリックした場合と同様に そのファイルへのエクスポートが行なわれます。
このリストの中のファイル名をマウスボタン1でクリックすると、 そのファイル名が Output Filename フィールドにコピーされます。 また、このリストの中のファイル名をマウスボタン1でダブル・クリックすると、 Export ボタンをクリックした場合と同様に そのファイルへのエスポートが行なわれます。 既に存在しているファイルへのエクスポートを行なった場合には そのファイルに格納されていた情報は失われることに注意して下さい。
このフィールドで return をタイプすると、 Rescan ボタンがクリックされた場合と同様に 現在のディレクトリがスキャンされます。 この文字列は、Language の選択に応じて設定されます
この内容は、Direcotries リストの ディレクトリ名をクリックするか、 もしくはキーボードから直接入力することによって変更することができます。 ディレクトリ名を入力した後に return をタイプすると、 Rescan ボタンをクリックした場合と同様に そのディレクトリの中のファイルがスキャンされ、 Alternatives リストの内容が更新されます。
``..'' は親のディレクトリを示しています。 親ディレクトリへの移動は、Alternatives リスト、 もしくは Directories リストの上で マウスボタン3をクリックすることによって行なうこともできます。
Default Filename とは異なる、 既に存在するファイルへのエクスポートを行なおうとした場合には、 エクスポートを行なうかどうかを確認するための確認ウィンドウが開かれます。 また、Default Filename とは異なるファイルへの エクスポートを行なった場合には、 そのファイル名が Default Filename に設定されます。
この解説は、Eric Masson (ericm@kirk.ee.mcgill.ca) によって書かれた文書に基づくものです。
xfig -specialtext -latexfonts -startlatexFont default
もし全ての図を Special フラグ と LaTeX フォント を選択して開始したいのであれば、.Xresources ファイルか あなたが使っているリソース・ファイルで次のように指定します:
Fig.latexfonts: true Fig.specialtext: true
xfig が生成でき、LaTeX が読むことのできる、 いくつかのフォーマットがあります。 ここでは3つのケースのみをカバーします:
これらの方法にはそれぞれの利点があり、同程度に容易に扱うことができます。 方法 (A) の利点は、全てが TeX 形式に含まれており、 DVI ファイルが必要な情報全てを保持することです。 (B) では出力に際して PostScript の全ての機能とフォントを使用できます。 (C) では PostScript の描画機能と、 LaTeX のテキストのタイプセット機能を用いることができます。
LaTeX 文書のプリアンブル (\begin{document} よりも前の部分) に、次の行を置きます:
\input{psfig}
プリアンプルは次のようなものとなるかも知れません:
\documentstyle[12pt,bezier,amstex]{article} % include bezier curves
\renewcommand\baselinestretch{1.0} % single space
\pagestyle{empty} % no headers and page numbers
\oddsidemargin -10 true pt % Left margin on odd-numbered pages.
\evensidemargin 10 true pt % Left margin on even-numbered pages.
\marginparwidth 0.75 true in % Width of marginal notes.
\oddsidemargin 0 true in % Note that \oddsidemargin=\evensidemargin
\evensidemargin 0 true in
\topmargin -0.75 true in % Nominal distance from top of page to top of
\textheight 9.5 true in % Height of text (including footnotes and figures)
\textwidth 6.375 true in % Width of text line.
\parindent=0pt % Do not indent paragraphs
\parskip=0.15 true in
\input{psfig} % Capability to place postscript drawings
\begin{document}
\end{document}
この方法で線を描画する場合には、 xfig 上での線の角度を 適切なものに制限するようにしなければなりません。 さもなくば、図を LaTeX フォーマットでエクスポートした際に、 xfig はそれを LaTeX が扱える最も近い角度で近似し、 通常は望ましくない結果が生じます。
このモードではテキストに LaTeX のコマンドを含めることができ、 LaTeX に取り込まれた際にそのコマンドは適切に解釈されます。 例えば:
$\int_0^9 f(x) dx$
は関数 f(x) の 0 から 9 の積分となります。
LaTeX ファイルを生成するためには、xfig の
File メニュー
から Export... を選択し、
エクスポートする Language として
LaTeX picture を選択します。
これによって .latex というサフィックスを持つファイルを生成し、
直接 LaTeX 文書に取り込むことができます。
例えば、次のコードはファイル yourfile.latex を 直接 LaTeX 文書に取り込みます:
\begin{figure}[htbp]
\begin{center}
\input{yourfile.latex}
\caption{The caption on your figure}
\label{figure:yourreferencename}
\end{center}
\end{figure}
図を描き終ったならば、xfig の File メニュー から Export... を選択し、 エクスポートする Language として Encapsulated PostScript を選択します。 これによって、次のような方法によって LaTeX 文書に取り込むことができる、 .eps というサフィックスを持つファイルを生成することができます。
\begin{figure}[htbp]
\begin{center}
\psfig{file=yourfile.eps}
\end{center}
\caption{Your caption}
\label{figure:yourreference}
\end{figure}
注意: 環境によってはこの方法は使用できないかも知れません。 また、この方法で生成される DVI ファイルは ポータブルではないものとなることがあります。
$\int_0^9 f(x) dx$
のように入力すれば、それは LaTeX で処理されます。
LaTeX で出力したいテキストについては
Special フラグ を ON にし、
PostScript で出力したいテキストについては
OFF にする必要があることに注意して下さい。
この方法を用いる場合には、 File メニュー から Export... を選択し、 エクスポートする Language として Combined PostScript/LaTeX (both part) を選択します。 これによって、次のような方法によって LaTeX 文書に取り込むことができる .pstex_t というサフィックスを持つファイルと、 PostScript のコードを含む .pstex というサフィックスを持つファイル を生成することができます。 .pstex_t ファイルは自動的に .pstex ファイルを取り込むので、 これを明示的に TeX ファイルに含める必要はありません。 図を取り込むためには、次のようなものを用います:
\begin{figure}[htbp]
\begin{center}
\input{yourfigure.pstex_t}
\caption{Your figure}
\label{figure:example}
\end{center}
\end{figure}
注意: xfig が生成した .pstex_t ファイルを 編集したいと思うことがあるかも知れません。 それは .pstex ファイルを完全なパスで参照することがありますが、 これはそれらのファイルを他のディレクトリに動かした場合に問題を生じます。 個人的には、完全なパス指定を削除し、 ファイル名のみを残しておくことを好んでいます。
もし .ps ファイルしか持っていないならば、 それを Encapsulated PostScript に変換するために GhostScript の ps2epsi を用いることができるでしょう。
必要であれば、 pstoedit を用いれば、 PostScript を Fig ファイルに変換することができるかも知れません。
図を
\input{file.psttext_t}
によって取り込みたいのであれば、図の大きさを指定する方法はありません。
これに対する、2つの解決方法があります:
\scalebox{factor}{object}
は、任意の比率でオブジェクトをスケーリングします。
比率は単純な数値 (1よりも小さければ縮小、1よりも大きければ拡大) です。
オブジェクトは、通常はいくつかのテキストやグラフィックです。
例えば:
\scalebox{2}{ \input{file.pstex_t} }
は、ドライバに依存して、図を2倍に拡大します。
ビットマップ・フォントをスケーリングすると醜い結果が得られるので避けること。
\resizebox{width}{ht} {stuff}
は "stuff" を width × ht の大きさにリサイズします。
パラメータとして "!" を用いるとボックスのアスペクト比が保存されます。
例えば:
\resizebox{5cm}{!}{fat cat}
は "fat cat" の幅を 5cm に、高さを適切に設定します。
(Lamport の本の 129ページより)
この機能を使用する場合には、クリックできるようにしたいオブジェクトに、 Edit パネル の Comments で、
HREF="url" ALT="string"
のような指定を行なっておくことが必要となります。 ここで、url はリンク先の URL、 string は イメージを扱わないブラウザのための代替文字列 (ALT アトリビュートは HTML 3.2 では必須となっている) です。 string は、xfig がイメージ・マップと共に生成する 代替テキスト・リンクのラベルとしても用いられます。
TEXT オブジェクトをリンクのために用いることはできません。 CIRCLE、ELLIPSE、SPLINE、及び ARC は多角形で近似されます。 POLYLINE や OPEN SPLINE などの開いたオブジェクトは 閉じられているものとして扱われます。 ARC-BOX は BOX と同じように扱われます。